- 一般眼科
近視の進行予防に関して
目次
子どもの近視進行を抑える5つの方法
はじめに
近年、子どもの近視が増加し世界的な問題となっています 。近視が強くなると将来緑内障や網膜剥離などの深刻な目の病気のリスクが上がることがわかっており 、「子どもの時期に近視を発症させない・進行させないこと」が生涯の視力を守る上で非常に重要です 。本記事では、近視進行予防法として、現在有効性・安全性が示されている5つの方法をご紹介します。それぞれの成長時期に応じた実施可能性や有効性、メリット・デメリット、副作用、そして自由診療として受ける場合の費用目安について解説します。
• 低濃度アトロピン点眼(近視抑制用の低濃度の目薬)
• オルソケラトロジー(夜間装用の特殊ハードコンタクトレンズ)
• 屋外活動(十分な自然光を浴びる生活習慣)
• レッドライト療法(近視抑制目的の低出力赤色光照射)
• EDOFコンタクトレンズ(Extended Depth of Focus、焦点深度拡張型コンタクト)
各ご家庭のお子さんの年齢や状況に合わせ、どの方法が適しているか検討する際の参考になれば幸いです。
低濃度アトロピン点眼
低濃度アトロピン点眼は、濃度を薄めたアトロピン硫酸塩の目薬を毎日さすことで、近視の進行を遅らせる治療法です 。もともとアトロピンは1%濃度のものが小児の弱視治療などに長年使われてきましたが、近視抑制目的ではその20~100分の1の超低濃度を使用します 。1日1回、就寝前に点眼するだけと手軽で、低濃度のため点眼後にまぶしさや手元のピントが合いにくいといった副作用もほとんどありません (濃度が上がるにつれて可能性は高まりますが)。近年の研究で、こうした低濃度アトロピン点眼は点眼しない場合に比べ近視進行を初年度に30~70%程度抑制できることが示されています 。2024年末には日本でも初めて近視抑制用途の低濃度アトロピン点眼薬(濃度0.025%の「リジュセア®ミニ点眼液」)が厚労省に承認され、2025年春から販売開始予定です 。
● 年齢別の適用: 一般的に低濃度アトロピン点眼は小学生頃から開始するケースが多いです。就学前の幼児でも近視が進む場合には医師の判断で点眼を検討することもありますが、近視は低年齢ほど発症例が少ないため幼児期に実施されることはまれです。小学生では近視の進行スピードが最も速いため 、この時期に点眼を始めると強度近視への進行リスクを大きく下げられると期待されます 。中学生~高校生になってからでも使用は可能ですが、思春期以降は身長と同様に眼球の成長速度(近視の進行速度)が緩やかになるため 、年長児ほど点眼治療の効果は相対的に小さくなる傾向があります。ただし、高校生でも近視が進んでいる場合には抑制効果が期待できるため、必要に応じて医師が点眼を勧めることがあります。
• メリット: 毎晩寝る前に1滴さすだけでよく、家庭で簡単に継続できます 。低濃度で副作用が軽微なため安全性が高く、世界的にも最も広く行われている近視抑制法です 。近視進行を平均で半分程度に減速できる有効性が報告されており 、早期から始めれば将来の強度近視リスク低減につながります。
• デメリット: 治療を続けている間しか効果が持続しないため、長期間の継続が必要です。点眼自体は対症療法であり近視を根本的に治すわけではないので、点眼中もメガネ等での視力補正は必要になります。また低年齢ほど効果が高い一方、思春期以降の進行が遅くなった段階では点眼の抑制効果も小さくなります 。点眼を中止すると進行が再加速(リバウンド)する可能性も指摘されており、適切な中止時期の判断が重要です。
• 副作用: 濃度が低いため副作用はほとんど見られません 。まれに瞳孔がわずかに開いて明るい所でまぶしさを感じる、手元が若干見づらくなる等が報告されていますが 、0.01~0.025%程度の低濃度では通常日常生活に支障が出るほどの副作用は起こりません。刺激感も少なく、小児でも安心して使用できます。
• 費用: 日本では保険適用外(自由診療)のため自己負担となります。点眼薬は1本あたり約3,000~4,000円(税込)(*2025年4月に発売のリジュセア®ミニ点眼液の価格はこれより1ヶ月あたりの価格が高くなる予定です)で、1本でおおよそ1か月前後使用できます 。加えて定期検査料がかかります(検査料が3,000円程度 )。年間の費用目安は5~6万円前後(診察代含む)と考えられます。
オルソケラトロジー(夜間装用コンタクトレンズ)
オルソケラトロジーは、特殊なデザインのハードコンタクトレンズを夜間就寝時に装用し、寝ている間に角膜の形をわずかに平坦化させて近視を矯正する方法です 。朝起きてレンズを外すとその矯正効果がしばらく持続するため、日中はメガネやコンタクトなしで生活できるようになります 。もともとは視力矯正(裸眼視力の改善)が目的の治療ですが、角膜形状を変えることで網膜周辺部にピントのずれを生じさせ、近視の進行(眼軸長の伸展)を抑制する効果もあることが分かっています 。実際、オルソケラトロジー装用開始から2年間で近視進行が平均で32%~63%程度抑制されたとの報告があります 。矯正できる近視の度数には限界があり、角膜への負担から適応はおおよそ-4D程度までの中等度近視とされています 。それ以上の近視度数になると、完全な矯正は難しくなります。
● 年齢別の適用: オルソケラトロジーは小学生から高校生まで幅広い年齢で実施されています。基本的に就寝中に装用し日中は外すため、低年齢の子どもでも保護者の管理下で夜間に装用させやすい点が利点です 。当院では、コンタクトレンズを装用する恐怖心を克服できる小学校3年生以上で開始するケースが多いです。それ以下では管理が困難なため当院ではおすすめしていません。中学生・高校生でも効果が期待できます。特に10代前半までの角膜が柔軟な時期の方が角膜形状が変わりやすく、年少児ほど進行抑制効果が出やすいことが報告されています 。一方、17~18歳以降は近視の進み方自体が緩やかになるため、オルソケラトロジー単独では進行抑制の必要性が薄れる場合もあります。
• メリット: 夜寝ている間に装用し日中は裸眼で過ごせるため、日中の視力矯正と近視抑制を両立できる点が最大のメリットです。日中にメガネやコンタクトを使用しなくて良いので、スポーツや外遊びも裸眼で思い切りでき、お子さんの活動の幅が広がります。また近視進行抑制効果も認められており 、特に低年齢から始めることで強度近視への進行を大きく減らせる可能性があります 。保護者の協力のもとであれば、小学生から開始しやすい治療と言えます。
• デメリット: レンズの装着・洗浄などお手入れに手間がかかります。適切な管理を怠ると角膜感染症を起こすリスクがあり、最悪の場合失明につながる重篤な合併症となりえます 。そのため毎晩のレンズ消毒や定期検診を厳守する必要があります。また、装用を中止すれば角膜形状は数日~数週間で元に戻るため 、効果を維持するには継続使用が必要です。矯正できる度数にも限界があり、近視が強すぎる場合(おおよそ-4~5D以上)や乱視が強い場合には十分な視力が得られないことがあります。レンズ装用開始から安定するまでの間、就寝中に異物感や痛みを訴える子もいますが、通常は数日〜数週間で慣れていきます。
• 副作用: 主なリスクは前述の角膜感染症です。夜間にレンズを装用するため症状の発見が遅れがちになることもあり、子どもが「目が痛い」「充血している」など訴えた場合はすぐ眼科を受診する必要があります。その他、レンズ装用により角膜に傷やアレルギー性結膜炎が生じることがあります。重篤な場合は装用を中止し、他の治療に切り替える必要があります。
• 費用: オルソケラトロジー治療は保険が効かず自費診療です。初年度は両眼で15~20万円程度が相場で、この費用に検査料やレンズ代(破損・紛失保証を含む)、初期の診察費用などを含むクリニックが多いです 。以降はレンズを2年ごとに交換する必要があり、その際に追加費用がかかります 。
屋外活動(自然光曝露)
屋外活動を増やす生活習慣は、近視の発症予防および進行抑制に効果があることが数多くの研究で示されています 。具体的には、日光の下で過ごす時間が長い子ほど近視になりにくく、仮に近視があっても進行が緩やかになる傾向があります 。逆に屋内で長時間近くを見る生活(ゲームや勉強など近業作業の過多)は近視を進行させるリスク要因とされ、現代の子ども達の近視増加の一因になっています 。屋外活動はこうした近くの作業時間とのバランスを取る意味でも重要です。
簡単に行えるため、すべての年齢のお子さんに推奨される基本的な近視対策です。就学前の幼児期から積極的に外遊びをさせることで、そもそも近視を発症するリスクを大きく下げることができます 。実際、1日2時間以上屋外で過ごす子どもは近視になりにくいとのデータがあり 、世界各国で学校の休み時間に外遊びを奨励・義務化する動きもあります 。
レッドライト療法(低出力赤色光治療)
レッドライト療法は、近年注目されている新しい近視進行抑制法です。特定の波長(650nm前後の赤色光)の弱い光を1日2回、各3分間ずつ目に照射することで眼軸長の伸びを抑える方法で、英語ではRLRL(Repeated Low-Level Red Light)療法とも呼ばれます 。2014年に中国で偶然この波長の赤色光に近視抑制効果があることが発見され、2021年に米国眼科学会誌にその高い有効性が報告されたことで世界的に大きな話題となりました 。使用する赤色光は低出力の可視光なので痛みなどは全くなく、家庭用の小型機器を用いて子どもが光源をのぞき込むようにして照射を行います 。ある研究では、平日のうち週4日以上きちんと実施した小児では近視進行が約9割抑制されたとの結果が報告されており、その効果の高さに驚きがもたれています 。これは現在報告されている中で単独では最も優れた近視抑制効果といえますが、また長期的な安全性は不明な点が多いです。
● 年齢別の適用: レッドライト療法は主に小学生~中学生を対象に検討されています。照射中3分間じっと光を見る必要があるため、ある程度の協力ができる年齢(目安として6歳以上)でないと実施は難しいでしょう。就学前の幼児への適用例はほとんどありませんが、もし幼児でも近視が強く進行が速い場合には、保護者のもとで短時間じっと光を見る練習をしながら導入を検討するケースもあるかもしれません。ただ一般的には小学低学年~中高生が主な対象です 。特に小学~中学年代で近視の進みが速い子に対して、大幅な進行抑制を期待して導入されます。高校生でも理論上効果はありますが、この療法自体が新しくエビデンスが限られるため、高校生以降での実施例はまだ少ないようです(近視進行がほぼ止まっている年齢では通常必要ありません)。いずれにせよ、成長期の子どもで近視が進んでいる場合に、他の方法で効果不十分なケースのセカンドラインとして検討される療法です。
• メリット: 非侵襲的(手術や薬剤を使わない)で痛みもなく、極めて短時間の照射で済む点が大きなメリットです。家庭用機器を用いれば自宅で好きな時間にできるため、生活リズムに組み込みやすいでしょう。報告されている近視抑制効果は非常に高く 、単独療法としては現時点で最も強力です。他の治療と異なり目に薬を入れたりコンタクトレンズを装用したりしないため、装用感や薬剤アレルギーの心配がなく、身体的な負担が少ない方法です。
• デメリット: 長期的な安全性が未確立な点が最大の懸念です 。理論上は低出力の可視光なので有害ではないと考えられていますが、新しい治療ゆえに眼への影響を長期間追ったデータが不足しています 。そのため現時点では慎重な経過観察が必須です。また、日本ではまだ承認されておらず実施できる医療機関が限られます。機器の管理を適切に行わないと照射時間を守れなかったり、子どもが嫌がってサボってしまったりと、家庭での継続が鍵になります。中国では医師の管理なしに市販され問題となった経緯もあるため 、必ず眼科医の指導の下で行う必要があります。
• 副作用: 照射中まぶしいと感じる場合がありますが、低出力の赤色「可視光」であり組織にダメージを与えるような強度の光ではありません 。ただし長期安全性が不明なため、照射による網膜やその他眼組織への微細な影響については今後の研究が必要です 。治療を受ける場合は定期的に眼科で眼底検査を受け、異常がないか経過を追うことが推奨されています 。
• 費用: 当院では取り扱いがなく、日本でもまだ導入実績のある施設は少ないため、費用は大きく施設によって異なると考えられます。
EDOFコンタクトレンズ(焦点深度拡張型ソフトコンタクト)
EDOFコンタクトレンズは、Extended Depth of Focus(焦点深度拡張型)デザインを採用した使い捨てソフトコンタクトレンズです 。もともと遠近両用コンタクトレンズ(多焦点コンタクト)は老眼矯正用として知られていますが、近視進行抑制効果があることも分かりました 。EDOFレンズは特殊な光学設計により複数の距離に焦点を作ることで、網膜周辺部にわざとピントのぼやけた光を当て、眼球がこれ以上伸びないよう働きかけます 。言い換えると、視界をクリアに保ちつつ周辺視野にはデフォーカス(焦点ぼかし)を与えることで近視進行を抑制する仕組みです。通常の単焦点コンタクトと比較し、EDOFコンタクト装用児は2年間で近視度数の進行が32%少なく、眼軸長の伸びも25%少なかったとの報告があります 。
● 年齢別の適用: ソフトコンタクトレンズですのでコンタクトレンズが装用可能になった年齢になれば適用となります 。具体的には、小学生でも高学年(10歳前後)くらいからが目安で、本人の性格や意欲によってはもう少し低年齢でも装用可能な場合があります。一般的には中学生以上であれば問題なく扱えるため、この年代で近視が進行している場合に処方されます。オルソケラトロジーがアレルギーなどの副作用で続けることが困難になった場合もこの治療を勧めることが多いです。
• メリット: 普通のコンタクトレンズと同様に日中の視力矯正ができ、メガネなしで生活できます。スポーツ時や見た目の面でメガネを嫌がるお子さんにも受け入れやすい方法です。オルソケラトロジーと違い日中装用ですが、使い捨てタイプなのでケアが簡単で清潔に保てます 。近視抑制効果はオルソケラトロジーや低濃度アトロピンには若干劣るものの、国内外でエビデンスが蓄積しつつある安全な矯正・治療法です。
• デメリット: 低年齢の子には装用が難しい点がデメリットです 。自分でレンズの付け外しができ、異物が入った際に対処できる年齢になるまで使えません。また、多焦点設計ゆえに見え方の質が単焦点レンズよりやや低下する場合があります。装用初期に遠くや近くがわずかにぼやけたり、夜間に光がにじんだりすることがありますが、多くは慣れるか許容できる範囲です。加えて、日中ずっとレンズを入れておく必要があるため、ドライアイ傾向のある子では長時間の装用が負担になることもあります。いずれにせよコンタクトレンズ装用に伴う自己管理が必要であり、レンズの扱いに不安がある場合は無理に開始しない方がよいでしょう。
• 副作用: 基本的には通常のコンタクトレンズと同様です。
• 費用: レンズ代は商品にもよりますが、例えばSEED 1dayPure EDOFの場合1箱32枚入りで税込4,400円程度です 。両眼で1か月あたり約2箱(約8,800円)、1年では約10万円弱のレンズ代となります 。
おわりに
以上、子どもの近視進行を抑制する5つの方法について、年代別の視点を交えて解説しました。それぞれ作用メカニズムや適した年齢、メリット・デメリットが異なります。お子さんの年齢や近視の程度、性格(レンズを嫌がらないか、きちんと継続できるか等)に応じて、最適な方法を選択していくことが大切です。また場合によっては複数の方法を組み合わせることで相乗効果が期待できることも分かってきました。例えばオルソケラトロジーと低濃度アトロピン点眼を併用すると、単独より約5割も進行抑制効果が高まるとの報告があります (実際院長の娘は小3より両方の治療を組み合わせて近視の進行予防に取り組んでいます)。よく相談しながら、安全に配慮して適切な近視抑制プランを立てていきましょう。お子さんの大切な目を将来のリスクから守るため、できることから早めに始めてみてください。近視と上手に付き合いながら、その進行を少しでも抑えて明るい視界を保っていきましょう。
参考文献・ガイドライン:日本近視学会「近視の進行抑制治療」 他.





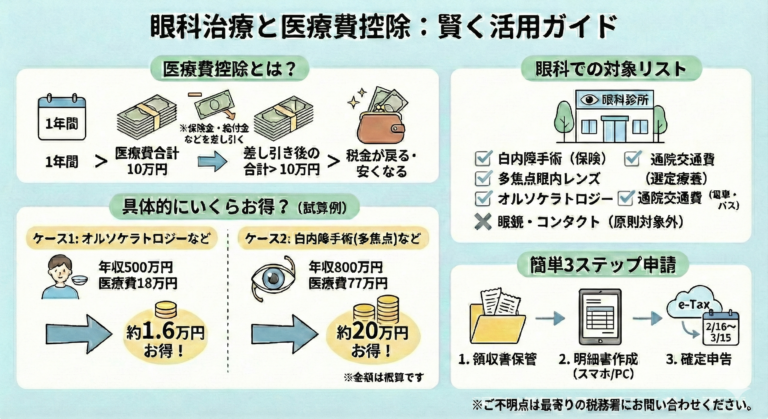

-768x432.jpg)





















