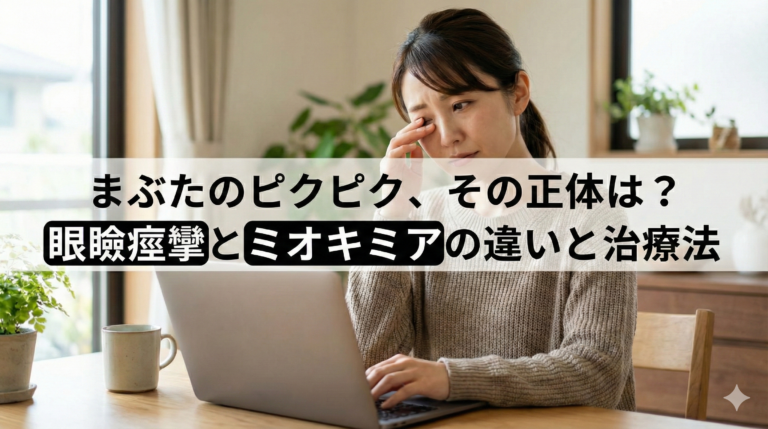- 網膜硝子体
中心性漿液性網脈絡膜症(CSC)とは?
中心性漿液性網脈絡膜症とはどんな病気?
中心性漿液性網脈絡膜症(Central Serous Chorioretinopathy, 略称CSC)は、網膜の中心部(黄斑)の下に液体(漿液)が漏れてたまり、網膜が局所的に隆起(網膜剥離)することで視力に障害を起こす疾患です 。突然に片方の目の中央がぼやけて見え、物がゆがんで見える(変視症)あるいは小さく見える(小視症)といった症状が現れます 。この病気は20~50代の比較的若い成人に働き盛りの男性に好発することが知られています 。原因は完全には解明されていませんが、近年ではストレスやステロイドホルモンの関与が指摘されており、生活習慣や体質が発症に影響すると考えられています 。
関連するリスク因子
日常生活や体の状態でCSCの誘因となり得る主な要因として、以下が挙げられます
• 強いストレス: 精神的緊張や過労など過度のストレスはCSC発症のリスクを高めるとされています 。実際、パイロットなど緊張の多い職業の人に発症しやすいとの報告もあります 。
• 喫煙:喫煙歴はCSC発症の大きな危険因子の一つです。発症した方でまだ喫煙されている方には強く禁煙を勧めます。
• ステロイド薬の使用: ステロイド系抗炎症薬の使用がきっかけで発症する場合があります 。クッシング症候群(体内でコルチゾール過剰な状態)でもCSCが生じることが報告されています 。そのため、治療中のステロイド薬がある場合は主治医と相談し必要に応じて減量・中止が検討されます。
• 睡眠不足: 慢性的な寝不足や夜更かしなど生活リズムの乱れもリスク因子と考えられています。十分な睡眠が取れていないと視力の回復が遅れたり後遺症が残ったりする場合があるため注意が必要です 。
• 妊娠: 女性の発症は男性より少ないものの、妊娠中にCSCを発症するケースが知られています 。これは妊娠に伴うホルモン変化が関与している可能性があります。
経過の特徴
CSCは多くの場合一過性(ある程度の期間が経つと軽快)で、数か月以内に自然に液体が吸収され視力が回復します 。典型的には発症から3~6か月で自然治癒し、治療をせずとも視力が元に戻ることが多いです。ただし再発しやすい病気でもあり、一度治っても数年以内に再発を繰り返す例があります。ごく一部の患者さん(全体の5%前後)では漿液のもれが長引いて慢性化し、網膜の下の層(網膜色素上皮)に萎縮が生じて視力低下が持続することもあります 。そのため、症状が続く場合や再発した場合には適切な治療介入が必要になります。
治療法
急性期(発症して間もない場合)の治療方針
CSCの急性期(発症してまもない時期)では、まず経過観察による様子見がとられることが多いです。
これは、上述の通り多くの症例で自然に液体が引いて視力が改善するためです 。
通常、1−2ヶ月程度の間隔で定期的に眼科で検査を受けながら、網膜下の液体が吸収されるのを待ちます。その間、以下のような生活上の注意が勧められます:
• 安静とストレス軽減: 無理な残業や過度の緊張は避け、心身の休養に努めましょう。ストレス管理は症状改善に重要です 。
• 禁煙:タバコを吸われている場合は禁煙をしましょう。タバコを継続したままだと、治療しても軽快しない、もしくは軽快してもすぐ再発します。
• 睡眠を十分にとる: 規則正しい生活を心がけ、睡眠時間をしっかり確保してください 。睡眠不足は網膜の回復を妨げる可能性があります。
• ステロイドの中止: 現在ステロイド系のお薬(点鼻薬や塗り薬も含む)を使用中の場合、CSC悪化の要因となり得ます 。自己判断で止めず主治医に相談し、可能であれば減量・中止や他薬への変更を検討します。
一般的には3から6か月程度は経過を見ます。この間に多くは改善しますが、視力が極端に低下して日常生活に支障が大きい場合などは、早めに治療を検討することもあります。
また急性期には循環改善薬などが使われることがあります。当院でも必要に応じて内服薬を処方しています。
ステロイド薬の投与は炎症性疾患で用いられる治療ですがCSCには無効であり、むしろ前述のようにCSCの誘因となるため使用しません 。
毎回の定期検査では、視力や眼底の状態をチェックし、網膜下液の量を観察します。
多くの場合、経過観察だけで十分ですが、半年近く経っても改善しない場合や再発を繰り返す場合には次の段階の治療を検討します。
慢性期の治療方針(積極的治療)
初期治療で改善せず慢性型に移行したケースや、再発を繰り返して視力低下が長引いているケースでは、網膜下の液体を吸収させるための治療を行います。積極的な治療介入によって、長期化による網膜組織へのダメージを防ぎ、視力の改善・維持を図ります 。主な治療法には以下のようなものがあります。
• レーザー光凝固術(レーザー治療)
造影剤を使用した検査を行い、漏れている場所(漏出点)を確認します。この漏出点が黄斑部から離れている場合、その部位にレーザーを当てて網膜下への液漏れをストップさせる治療です。レーザー照射により漏出点の網膜色素上皮に軽い熱傷を与え、周囲の組織が治癒過程で新たに成長・再付着することで漿液の漏出を止めます 。これにより網膜下の液体吸収が早まり、自然経過より短期間で視力が回復する効果が期待できます 。比較的簡便な治療ですが、照射した部分には瘢痕(やけど痕)が残り視野の一部に小さな暗点が生じる可能性があります。そのため黄斑(中心部)に近い箇所には適用できません 。
• 光線力学的療法(PDT)
PDTはビスダイン(ベルテポルフィン)という光感受性の薬剤を静脈注射し、数分後に特殊な低強度レーザーを眼底の患部に照射する治療です。薬剤が漏出部位の脈絡膜血管に集まり、レーザー照射によって活性酸素を発生させることで、異常に透過性が亢進した脈絡膜の血管内皮などをダメージし、血管の過剰な漏出を沈静化させます 。この結果、網膜下液の吸収が促進され、液体が消失し視力が改善したとの報告があります 。PDT後は一時的に視力が低下したり暗く感じたりすることがありますが、これは一過性であり最終的な視力改善には影響しません 。PDTの全身副作用としては、光感受性物質を使う関係上、治療後数日間は強い日差しを避ける必要がある程度で、体への負担は小さいです。PDTは視力に影響のある黄斑下の漏出でも適用可能でありますが、現状として日本では保険適用外の治療になります。
以上のように、CSCの治療法は病状の経過によって段階的に選択されます。
急性期のCSCではまず十分な経過観察と生活指導によって自然回復を促し、慢性型や再発例ではレーザーなどの専門的治療を検討します 。各治療法には効果とリスクがあり、患者さんの黄斑部の状態や職業・生活ニーズに応じて最適な方法が選ばれます。
治療後も再発の可能性はあるため、定期的な通院で経過を追いながら、ストレスの少ない生活や十分な睡眠など再発予防策に取り組むことが大切です。もし視野の中心に異変(ゆがみやぼやけ)が再び生じた場合は早めに眼科医に相談しましょう。